ソリストコースの「作曲家と作品分析」13回目。
ショパン、リスト、バルトーク、ラフマニノフ、ブルックナーなどを取り上げてきましたが、今日は新ウィーン楽派の3人。
シェーンベルク、ウェーベルン、ベルク。
まず、初めに、この時代の曲のイメージを尋ねると4人皆口をそろえて
「シャープな感じ」「冷たい感じ」「表情がない感じ」
という答え。
たしかに、調性の音楽に見られるような音関係がないので、「感情」の否定のような印象を受けるのですが、実際に音にしてみると、そう単純には言い切れません。
セリーによって順番に現れてくる音、
鏡を置いたよう、逆行する音列、
極端な不協和音の連続の中から立ち上る不思議な雰囲気、
・・・・
耳を澄ませると、先入観が徐々に取り払われ、「感情」が立ち現れていきます。
それが演奏する人間からにじみ出るものなのか、音の響きから生まれるのか、音と音の連続から生まれるのか、音に対する記憶の中から感情が立ち上るのか・・・
理由は自分にもわからないのですが、弾いたり、聴いたりしている学生たちもハッとするような、ある種の「感情」がそこにはあるのです。
ブルックナーやマーラーなど後期ロマン派の時代を経て、無調への道をたどり、「ロマン」や「感情」といったものが否定されているかの様相を見せるのですが、実際には、ウェーベルンのヴァリエーションは温かく、ベルクのソナタは叙情性に満ち、シェーンベルクでさえ、心の奥深いところからの「情」が色となって現れるかのように感じられます。
卒業後、10年ほど師事していた間宮芳生先生にウェーベルンの変奏曲をレッスンで持っていったとき、
「この曲は、ものすご~くあったかい曲なんだ。それを演奏家が”現代曲”として片付けて冷たく弾くのは大いなる間違い!」
とおっしゃったことがありました。
今日、あらためてその言葉が蘇り、そのとき弾いたときより大きな共感をこの曲に対して持ちました。
深い内容を持った古典は、年齢を経て解釈が深まる、といわれますが、現代曲や無調の音楽も、何度も弾きこみ、体内に吸収していく中で、今まで見えていなかったものが見えてくるように思えます。

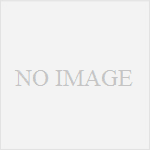
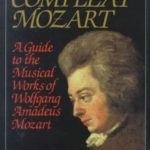
コメント