富田庸先生による「ロ短調ミサとバッハ研究 ~作品の伝承と編集しから見る研究上の諸問題~」と題された講演が国立音大の110スタジオで行われました。
英国クイーンズ大学教授であり、バッハ研究の最先端の現場に立っていらっしゃ富田先生の講演は、昨年に続き、バッハ演奏研究声楽部門の一環として行われました。
研究者の方たちだけでなく、来年1月15日に演奏されるロ短調ミサに出演の声楽家など演奏の現場に立つ者にとっても、多くの示唆に富む講演でした。
国立音大図書館の充実した資料は、富田先生も来日時に利用されておられるそうで、あらためて国立音大の恵まれた知的環境を感じました。
ロ短調ミサを通じて19世紀の初版から新バッハ全集の改訂版までの検証、手稿譜、自筆譜、文書などの資料研究の最前線の状況など。
バッハ自身による自筆譜のインクは、鉛の度合いが高く、息子のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハが手を加えた音符のインクは、鉛がない、など刑事事件を解決していくようなスリリングな解明方法で、驚きました。
カール・フィリップは、ほとんど容疑者として扱われている感じなのですが、モーツァルトなどもこのインクアナリシスによって作曲年代が変更されるに至った経緯は有名です。
カール・フィリップが手を加えたことによってまるで異なる響きになっている箇所などに遭遇しますと、演奏家としての立ち位置を自分でどう決めるかが問われます。指揮者の「正直迷っています」という誠実な言葉は、大いに共感を呼ぶところでした。
ショパンにしてもまったく異なる楽譜が同時に混在している事実があり、今後、演奏家のとるスタンスは、
最新テクノロジーによって新たな事実が浮き上がるたびに、新しい判断と選択が迫られることになるでしょう。
参加された研究者の方たちの議論の場ともなり、学会の一コマを見るような雰囲気で、最後は、研究の成果が正確に書かれた楽譜を選ぶ、ということで落ち着きそうになったとき、その一件落着ムードが音を立てて崩れるような発言があったのです。
「僕たちは、いろいろ研究成果や過程なんか見たくないんです。演奏するとき、そういういろんな情報が目に入らないほうがいい。むしろ邪魔なんです。何も書かれていない楽譜のほうがよほど歌いやすい」
発言されたのは、テノール歌手の方。
一瞬みんなぎょっとしたのですが、バッハの楽譜は絵として見ても美しいことで知られており、そういう芸術的な音符の姿のほうがイマジネーションがわく、という意見は、演奏者の実感を伝えているようにも思えました。


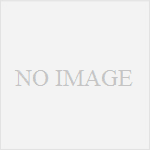
コメント