神奈川県民ホールで行われたウィーン国立歌劇場の「フィガロの結婚」。
ペーター・シュナイダー指揮、ジャンピエール・ポネル演出。
カルロス・アルバレスの伯爵。
バルバラ・フリットリの伯爵夫人。
シルヴィア・シュヴァルツのスザンナ。
アーウィン・シュロットのフィガロ。
とても良い舞台でした。
何か目新しいことがあるわけでもない、けれどモーツァルトの音楽そのものが決して古くないわけなので、何か新しいことをする必要はないんだ、ということを感じる時間でした。
会場のみなが幸せになるような、おそらくモーツァルトが望んだであろうオペラ。
そういう雰囲気が県民ホールを包みました。
スター歌手一人が突出しているような舞台ではなく、全体のアンサンブルの妙で聴かせてくれました。演出はオーソドックス。衣装も最近流行りの現代演出ではなく、落ち着いた品の良い舞台。
奇をてらう、というのは、モーツァルトの演奏には禁物だと思っている私としては、とても楽しめる舞台でした。
フィガロがGパンで出てきたり、伯爵が背広姿だったり、伯爵夫人がショッキングピンクのネグリジェだったりする・・・そこに何かメッセージがあるのはわかっても、モーツァルトの音楽以上の、というか、モーツァルト以外の何かを表現しようとするものが見えてしまうと、なんだか白けてしまうのです。
伯爵夫人の気品は、貞淑の象徴、白いドレスで良いと思うのです。
舞台にかかわる人すべてから、モーツァルトの音楽より前に出よう、という意識が感じられない ― その結果、モーツァルトの音楽の力が最も発揮され、人間模様と楽曲の美しさが舞台からにじみ出て、人生って素晴らしい、生きているということは楽しい、と思えるような時間になりました。
筋は決して単純とは言えないけれど、小難しい理屈なんかよりも、そんなシンプルな人生観が、モーツァルトの根底にあったのではないか、と最近思っています。
今回は、マルガリータ・グリシュコヴァ演じるケルビーノに熱い拍手が起きました。
日本のモーツァルトファンのケルビーノイメージにピタッとはまった感じです。
青春の危うさを、震えるようなピアニッシモで表現していました。
ケルビーノに限らず、今回の演奏で印象に残るのは、ピアニッシモでした。ふだん元気に歌うような箇所であえてピアニッシモを使い、それにオーケストラも協力する。延々とフォルテで美声を聞かせ続ける舞台に慣れた人には、静かすぎると感じる方もおられるかもしれませんが、県民ホールの音響も助けてか、非常に美しい演奏として心に残りました。
惜しむらくは、序曲など、オーケストラの音が少しずれていたり、時折、歌とずれたりして聴こえたことです。
これは、客席の場所のせいなのかもしれないので、断定は避けておきますが、伯爵が許しを乞う場面、その直前の「間」が、あともうほんの少し長くほしかった・・・と感じました。ここでそれまでの関係が逆転し、空気がすべて変わる一瞬なのですが、これがちょっとでも早いと、「ありえない筋書」のほうが前面に出てしまう・・・。
いずれにせよ、ハードワークの一日。舞台からエネルギーをもらって帰途についた一日でした。

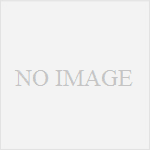
コメント