モーツァルト生誕250年からあっという間に10年。今年2016年は生誕260年にあたります。
今日は、神戸にあります関西国際文化センターのコスモホールでの講演会。天才ピアニストとしてのモーツァルトにスポットを当て、神童、青春、円熟、晩年それぞれの時期の作品をご紹介させていただきました。
新たなフォルテピアノとの出会いや楽器への習熟が、作品の成熟へとつながったモーツァルト。その変遷を追った90分でした。
民音博物館には、モーツァルト時代のヴァルター・ピアノのオリジナル楽器が常設されています。会場には、楽器への深い関心をお持ちの方々も多くご来場くださり、熱心にお聴きくださいました。
プログラム最後の曲「グラスハーモニカのためのアダージョKV356 」の演奏を終え、質問コーナーに。
お一人目は、「モーツァルトがベートーヴェンの頃まで生きていたらどんなピアノ曲を書いたか?」でした。
まず、ピアノ曲に関しては、楽器の限界ギリギリまで使う人ですので、楽器の発展とともに音域5オクターブ以上の曲を作ったことは間違いありませんし、楽器のパワー増大とともにドラマティックな要素が増えたかもしれません。
けれどやはり、モーツァルトの美学は、ウィーン式アクションの繊細で透明感のある楽器と一体になったもので、これ以上ぴったりはまる楽器はないように思えるのです。
「モーツァルトが1792年以降もずっと長生きしてベートーヴェンとピアノの弾き比べをしたらモーツァルトは負けるだろう」とある作曲家の先生が仰っておられましたが、イギリス式(打ち上げ式)のパワフルな楽器で強烈な演奏をしてベートーヴェンと腕比べするモーツァルトは想像しにくい(したくない?!)気もします。
ピアノの詩人ショパンに関しての質問もあり、アンコールはベートーヴェン「エリーゼのために」とショパンの「夜想曲」を追加。お別れに「トルコ行進曲」を終えピッタリ90分となりました。
雨の天気予報が外れ、降られずにすんだ秋の日の講演会。本日は私の生誕?年の誕生日でもありました。
皆様との出会いに、あらためて御礼申し上げます。


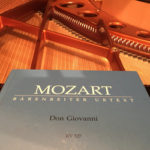

コメント